デジタルネイティブ最前線-小学生にコミュニケーション教育を-
|
秋田 義一
一般財団法人 AVCC 理事
一般社団法人 話力総合研究所 理事長
|
最近、人と直接かかわる機会が減っていると感じています。オンラインの会議、セルフレジ、端末機による注文など便利な道具の登場で、人とかかわらなくても目的を果たせる社会になってきています。コミュニケーション能力を考えるうえで、たいへん心配なことです。
人とかかわる機会が減るということは、コミュニケーションの訓練の場が減るということです。私たちは人とかかわることで意識せずともコミュニケーション能力を高める訓練をしてきました。しかし、これからの時代・・・生まれながらにデジタルに触れて育つ、いわゆるデジタルネイティブにとって、意識的にコミュニケーション能力を高める訓練の場を持つことが必要になってくるのかもしれません。
先日、旧知の小学校のH先生から連絡がありました。『秋田さんの「一生使える話し方の教科書」を読んだ。今、小6の担任をしている。これからの時代、コミュニケーション能力が必要だ。こどもたちに話してもらえないか?』とのことでした。
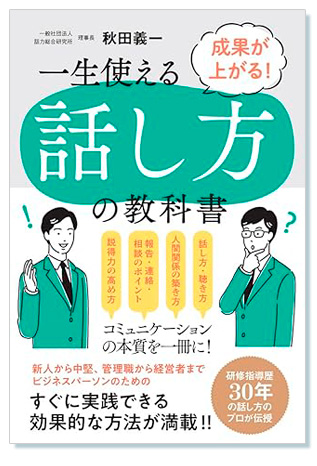
一生使える話し方の教科書 成果が上がる 秋田 義一 (著)
出版記念トークイベントの動画はこちら
良い話なので、すぐに引き受けました。翌週に45分間。6年生3クラス100名以上を体育館に集めて話をしました。過去に中学生や高校生にコミュニケーションの研修をしたことはありましたが、小学生には初めてです。
最初のひとことでこどもたちの気持ちをつかめるかが、良い雰囲気で最後まで聴かせ続けられるか否かをわけるポイントです。
「こんにちは。秋田義一です。みんなにとって、目の前の人はおじさんですか?おじいちゃんですか?」
「おにいさん!」
「みんな、ずいぶん気を使ってくれるね~」
「(笑)」
「おにいさんはさすがに言いにくいから、おじさんでいいかな」
「いいで~す」
「でも、みんなのおじいちゃんよりも年上だと思うよ」
「え~っ、いくつ~!?」
うまくいった!
「おじさんは主に3つのしごとをしています。ちょっと変わっています・・・」
「え~っ」
「大学の教員、防災コンサルタント、コミュニケーション能力を高めるための大人の塾」
持ち時間は45分、多くを語れる時間的余裕はありません。そこで、コミュニケーション能力(話力)を高めることが大切なこと、話力の磨き方としての基本要素、表現の原則(感じよく)、みんなと仲良くするためのあいさつ、返事。そして、困ったときには協力を求めよう。以心伝心は期待できない。「助けて」とことばを発することが大切。最後に、時代がどんなに変わろうとも、コミュニケーション能力を高めることの大切さは変わらない。社会で活躍している多くの人が、話力を学んだ直後に「もっと若いうちに学んでいればよかった」と言っている。これからも多くのことを学びながら、話す聴く能力も高めていくことを忘れないでほしいと言って締めくくりました。
当初、退屈しないか、理解できるかと心配でしたが、杞憂でした。こどもたちの反応がすこぶるよかったのです。笑うところで笑い、全体質問にはみんなで手をあげ、個別質問にもハキハキ即答します。たいへん気持ちよく、楽しく取り組めました。約束の時間に締めくくりましたが、先生が「質問のある人?」小学生だから質問は出ないだろうと思ったのですが・・・またまた期待を裏切ってくれました。
「コミュニケーションで失敗したことありますか?」
「周囲の雰囲気を悪くしてしまったらどうしたらよいですか?」
「失敗してしまったらどうすればよいですか?」
質問が出ること出ること・・・しかも、グッドクエスチョンばかりです。
ようやく終わった。と思ったら、驚いたことに30人くらいのこどもたちに囲まれました。握手してください。サインしてください。私が先、僕が先・・・
みんな教室に戻らないといけないのに・・・
「先生!いいんですか?」と、聞いてみるも、先生は見て見ぬふりです!?
30分くらいして、ようやく解放されました。
校長室に戻って待っていると、H先生が自分のクラスの分だけだけれどと、感想文を見せてくれました。お~、結構理解している。来年はみな中学生。今日の話を生かし成長してくれるでしょう。
学校を後にするときにH先生が見送ってくれ、「大人にする話とはだいぶ変えてくださったのですね。」と声をかけてくださいました。
それはそうです。ゲームや給食やともだちとのやり取りを例にしました。わからないので、その場でこどもたちに訊ねながら例にしました。
私は、笑いながら「いつもの三倍考えましたよ。」と答えました。
小学生からコミュニケーションの教育をすることができる。いや、鉄は熱いうちに打てです。デジタルネイティブ最前線の小学生にコミュニケーションの教育を体系的に行うことが、これからの時代、特に大切になってくると、あらためて感じました。
|