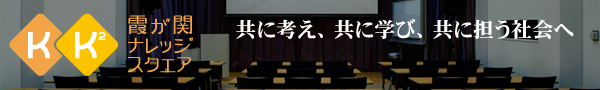KK2
weekly【メッセージfromKK2】
(第395号 2015年10月16日発行) by AVCC
※メールマガジンはHTML形式で配信しております。メーラー(メール送受信の仕組み)の種類や設定により正しく表示されない場合があります。※当メールには返信できません。お問い合せ・イベントの申し込みはそれぞれのコーナからお願いします。

オンスケジュールにオンディマンドをMIX - パラダイムの重層化 -
伊庭野基明
グローバルキャリアカウンセラー
グローバルキャリアカウンセラー
 先月に続き大学生の就職・採用活動の近況から、課題と今後の方向性を考えてみます。
先月に続き大学生の就職・採用活動の近況から、課題と今後の方向性を考えてみます。マイナビ社調査で、9月末での内定率が約80%となり、10月1日の内定式を境にほぼ本年度の就職・採用活動は山を越えつつあるようです。今年は「学業への専念」という観点で、企業が学生への正式な接触をすることを4か月間遅らせるという変更がありましたが、逆に水面下の活動が早まり実質就職活動期間が延びたという指摘もあり、経団連では来年度での見直しも視野に入れると言っているようです。
さて、就職協定の歴史は意外に古く1950年代の高度成長期に遡りますが、日本の学校制度から社会制度に至る現代の各種システムは、明治、昭和期の社会の合理化推進の結果としての制度が基礎になっています。ここで合理化とは社会学的にはマニュアル化であって、オンスケジュールでものを効率的に動かす事と言われます。しかし、今世界がこれだけ多様化し変化が常態化する中で、オンスケジュールというパラダイムのみでなく、需要と供給をオンディマンドでマッチングさせる仕組みも並行して考えるべきでしょう。
例えば、就職・採用の分野では以前KK2のイノベーションプログラムで何回か発表があった、全在学期間にわたるインターンシップ(コーオプ)や、日常での地域と学生の交流などの産学連携でのオンディマンドの接触が、オンスケジュール制度の良い部分を残し新しい視点を加えるという重層的運用の中での相乗効果を生むのではないでしょうか。
このような産学でのしくみの中で、企業が学生に望みながらも大学では教えてこなかったコミュニケーション能力の向上などを図るため、KK2では社会横断的な学びの場を提供する事を心がけています。10月31日(土)開催予定の「しごと力道場」もその一つで、討論形式で対話力UPを図る少人数での研修プログラムです。定員に近づいておりますが、ぜひ参加をご検討ください。
■発行元:一般財団法人高度映像情報センター(AVCC)霞が関ナレッジスクエア事務局
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館奥エスカレーター上がる
電話:03-3288-1921 FAX:03-5157-9225
■発行者Webサイト:http://www.avcc.or.jp/ http://www.kk2.ne.jp/
■登録情報変更及びメルマガの登録停止:※ログインして解除して下さい
https://www.kk2.ne.jp/header_link/member_updateEzine.html/
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館奥エスカレーター上がる
電話:03-3288-1921 FAX:03-5157-9225
■発行者Webサイト:http://www.avcc.or.jp/ http://www.kk2.ne.jp/
■登録情報変更及びメルマガの登録停止:※ログインして解除して下さい
https://www.kk2.ne.jp/header_link/member_updateEzine.html/