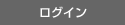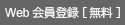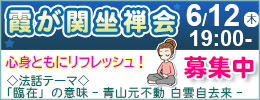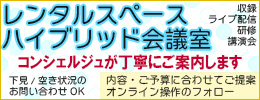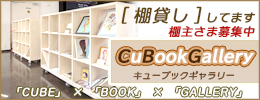『「若作りうつ」社会』 (熊代 亨 著)
-
■若さ志向で年の取り方がわからなくなっている社会
若作りのための化粧品やサプリメントが溢れる日本社会では、思春期のような心持ちと生活を維持するのはさほど難しくはない。しかし、平均寿命が延びたとはいえ、身体が衰え始める時期が以前と比べて大きく変わったわけではない。誰もが若作りをするようになった今日、生物としての加齢と社会的・精神的な加齢とのギャップが広がり、心身に負担を強いている。そして、そうした負担が引き金になって精神疾患に至った、「若作りうつ」とでもいうべき症例が増えている。
本書では、精神科医である著者が、年の取り方がわからなくなり、寄る年波に足がすくんでしまっている現状について、ミクロ(個人)とマクロ(社会)の両面から考え、過去に遡って原因を検証し、未来に向かって何をすべきか模索している。 -
■年の取り方がわからないなら、上下の世代と学び合おう
例えば、Eさん(60歳・女性)は看護師長を務め、精力的な働きぶりで知られていたが、小さな脳梗塞が見つかる。約2ヵ月で職場復帰するも、昔と同じペースで働けない自分自身を情けなく感じるようになり、やがてうつ病になってしまった。これは「若い頃のライフスタイルを引っ張っているうちに身体がついてこなくなった」ケースだ。
こうした「若作りうつ」な人達の治療には、ライフスタイルの見直しや年を取った自分自身を受け入れる過程が不可欠である。かつて、年齢ごとに社会的役割や活動内容が定められていた社会では、そうした心理的ギアチェンジは社会によって決定されていたが、現在では、年の取り方は個人の自由に委ねられている。
メンタルヘルス上のリスクを自発的に回避するためには、世代間の相互影響を重視することが大切なのではないだろうか。年長者が年少者を育てるだけでなく、年少者によって年長者が育てられている点もある。身近な年長者・年少者とのコミュニケーションを大切にし、学んだり教え合ったりして生きていくことが「年の取り方がわからない社会」にいちばん有効な処方箋なのかもしれない。 -
◎著者プロフィール
1975年、石川県生まれ。信州大学医学部卒業。精神科医。専攻は思春期・青年期の精神医学、特に適応障害領域。地域精神医療に従事する傍ら、臨床現場で目にする“診察室の内側の風景”とインターネットやサブカルチャーの現場で目にする“診察室の外側の風景”の整合性にこだわり、ブログ『シロクマの屑籠』にて社会心理学的な考察を続けている。著書に『ロスジェネ心理学――生きづらいこの時代をひも解く』(花伝社)などがある。