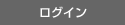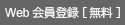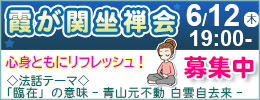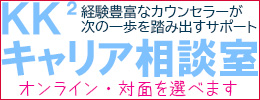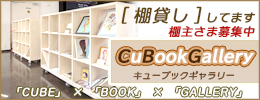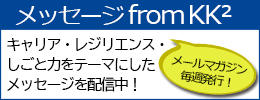『ニッポンには対話がない』 (北川 達夫/平田 オリザ 著)
-
■ コミュニケーションを軸に日本の社会と教育の再生を探る
グローバル社会だけでなく、日本国内においてもさまざまな価値観が交錯する現代、同質性や共通する時代の空気を前提とした、これまでの日本人のコミュニケーションが成立しなくなってきている。では、いまの日本に足りない「対話」「コミュニケーション」とはどういうものか。またそれを成立させる能力をはぐくむ「教育」はどうあるべきか。本書では、まったく異なる立場から「教育」や「表現」に携わる2人が、コミュニケーションを軸とした日本の「社会」と「教育」の再生の方向性を探るべく「対話」を行っている。
北川氏、平田氏の両者がともに強調するのが、まず価値観や意見の「違い」を前提とすること、その違いをすり合わせて妥協点を探っていくという姿勢の重要性だ。北川氏は、日本の教育現場では意見の対立や選択を避けようとする傾向があることを、平田氏は、中高年の男性が若い人の意見を押さえつける発言をしがちなことなどをそれぞれ指摘する。 -
■「違い」「対立」を前提とする「エンパシー型コミュニケーション」
日本人が発想として取り入れていかなくてはいけない概念として北川氏が提唱するのが「エンパシー(自己移入)型コミュニケーション」。これまでは、「シンパシー(感情移入)型のコミュニケーション」、すなわち、相手の気持ちを慮り、相手にも自分の気持ちをわかろうとしてもらえることを前提とした対話に焦点があたりがちだった。エンパシー型では「いくら察しようと努力しても、結局は相手の気持ちはわからない」ことを基本とする。そして、それならば、「もし自分がその立場だったら、どう考えて行動していくか」を考えていき、互いのその考えを「対立」させることから新しい何かを生み出していくのだ。日本人は合意できるところから積み上げていく傾向にあるが、ヨーロッパ人はまず対立点を積極的に見つけることから始める。対話によりお互いが「変わっていく」プロセスを楽しめるかがポイント、といった点において2人の意見は一致している。
-
◎著者プロフィール
北川 達夫:
フィンランド教材作家、教育アドバイザー。早稲田大学法学部卒業後、外務省入省。ヘルシンキ大学に学び、フィンランド専門官として養成される。在フィンランド日本国大使館、在エストニア日本国大使館勤務を経て、国際的な教材作家として活躍。
平田 オリザ:
劇作家・演出家、劇団「青年団」主宰。大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授。1995年に『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞を受賞。