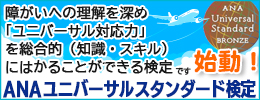『日本と出会った難民たち』 (根本 かおる 著)
-
■対応が遅れ、関心も低い、日本へ渡った「難民」の問題に迫る
国家権力から迫害を受け、他国の庇護を求める「難民」。日本では、その受け入れ数も、人々の関心も著しく低い。本書ではその現状とともに、難民(申請者含む)たちの日本における生活や支援の実態をリポート、日本社会と難民たちが共生する道を探っている。
1951年国連採択の「難民の地位に関する条約(難民条約)」には日本も批准している。批准国は条約の定める「難民」(条約難民)に該当するかを審査するのだが、日本では年間2500人ほどの申請があるものの、認定はわずか十数人。審査をする入国管理局が「難民を守る」よりも「不法な入国・滞在を防ぐ」という見方をしがちなのがその理由とみられている。
「条約難民」として認定されればさまざまな公的支援が得られるが、審査を待つ「難民申請者」は日本で厳しい生活を強いられる。決められた期間が過ぎて不法滞在や不法就労と判断されれば、施設への収容や強制送還も覚悟しなければならない。 -
■厳しい生活を送る難民・難民申請者に民間の支援の輪が広がる
厳しい環境にある難民や難民申請者に、民間から支援の輪が広がってきている。弁護士たちのネットワーク、無償で治療を行う歯科医師など。企業においても、たとえばユニクロは、正規雇用も視野にインターンとして難民を受け入れる制度を設けている。また、東京都のネイルサロン「アルーシャ」は、飲食店アルバイトなど単純労働にしか就けない難民女性に日本語やネイルアートの技術を教え、ネイリストとして雇用している。
著者は、難民のもつ可能性に注目すべきと訴える。難民たちは大きな喪失を乗り越えながら力強く生きている。また彼らは、命のともしびをつなぐなかで、「人間にとってもっとも大切なもの」を肌で理解し、人権感覚にも優れている。さらに、難民の中には、地位や教育のある「エリート」も少なくない。こうした生命力にあふれ、可能性に満ちた難民たちを受け入れ、交流をはかることが、日本社会の「多様性」の経験値となるのだ。 -
◎著者プロフィール
ジャーナリスト。東京大学法学部を卒業後、テレビ朝日にてアナウンサー、報道記者として勤務。米国コロンビア大学国際関係論大学院で修士号取得。1996年からUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)職員として難民援助の最前線で支援活動にあたるとともに、ジュネーブ本部で政策立案や民間部門からの活動資金調達のとりまとめを行う。WFP(国連世界食糧計画)広報官、国連UNHCR協会事務局長も務めた。2012年より現職。