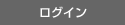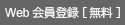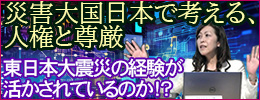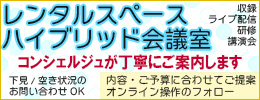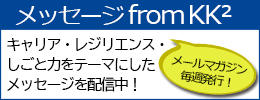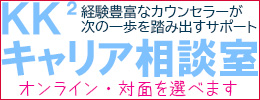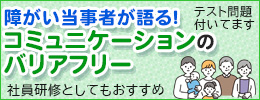『ソーシャルインパクト』 ‐価値共創(CSV)が企業・ビジネス・働き方を変える(玉村 雅敏 編著)
『ソーシャルインパクト』 ‐価値共創(CSV)が企業・ビジネス・働き方を変える

-
■ソーシャルな仕組みをつくり、社会的な投資に活かす
Facebookなどのソーシャルメディアを活用し、ビジネスの手法で社会課題の解決に取り組む事例が増えている。「社会的なことは儲からない」と思われがちだが、近年、その儲からないはずの分野から続々とビジネスチャンスが生まれているのだ。本書では、ネットワークを機能させ、価値共創の好循環を生み出す「ソーシャルインパクト」の考え方とその実践事例を紹介。そこから得られる示唆を解説している。
最近では、クラウドファンディングといわれる、ある目的や志などのため不特定多数の人から資金を集めるネットサービスが普及しつつある。他者の共感を得ることで資金を集める試みだが、プロジェクトの実現に向けて、出資者が協働して体制をつくり上げる動きも見られる。ソーシャルな仕組みをつくり、それをマーケティングや社会的な投資に活かそうという動きは広がる一方だ。共感によってつながり、支援し合うという、共感の連鎖が価値を増幅させる時代が始まっている。 -
■現場発の動きからはじまったヤマト運輸の「プロジェクトG」
東日本大震災が起きた直後、ヤマト運輸がいち早く被災地における救援物資輸送の支援で活躍したことは広く知られている。これらの支援活動は、じつは被災地で働くドライバーの自発的な動きからはじまっている。また、東北地域での取り組みとして有名な「まごころ宅急便」という活動もある。宅急便の配送時に、届け先の高齢者の安否確認を行い、体調などの不具合がある場合に社会福祉協議会へ連絡するというものだ。これは、ある女性ドライバーが懇意にしていたおばあさんの孤独死に直面し、「ヤマトの集配ネットワークを活かして、高齢者の孤独死をなくすことができないか」と思い立ち、はじまったサービスである。
このような現場発の動きからはじまった活動が「プロジェクトG」だ。「G」はGovernment(行政)に由来し、通常のヤマトの配送ビジネスをベースにしながら、地域の課題の解決などを行政や地域の企業、住民と連携して進める活動である。 -
◎編著者プロフィール
玉村 雅敏:慶應義塾大学総合政策学部准教授。博士(政策・メディア)。文部科学省科学技術・学術政策研究所客員研究官、内閣官房地域活性化伝道師などを兼務。専門分野はソーシャルマーケティング、公共経営など。
-
◎著者プロフィール
横田 浩一:横田アソシエイツ代表取締役、流通科学大学特任教授。日本経済新聞社を経て、2011年より現職。公益社団法人日本経済研究センター特任研究員も務める。
上木原 弘修:博報堂PR戦略局シニアマーケティングディレクター。日本広告学会会員。一般社団法人プロジェクト結コンソーシアム理事。
池本 修悟:一般社団法人ユニバーサル志縁社会創造センター専務理事、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパン副代表。一般社団法人社会創発塾代表理事、慶應義塾大学SFC研究所上席所員なども務める。
小島 敏明:株式会社乃村工藝社営業開発本部企画開発部部長、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授。