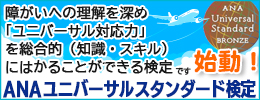『ぼくの命は言葉とともにある』(福島 智 著)
-
■「コミュニケーションの光」に救われた盲ろうの東大教授による人生論
視覚も聴覚も失った「盲ろう者」として世界で初めて常勤の大学教授になった著者。18歳で光も音もない宇宙空間に一人っきりで漂っている世界に放り込まれたが、周りの人々から「コミュニケーションの光」が射すことで絶望の淵から「生きる意味」を見出す。本書では、そうした経験や、そこから学んだ人生論、幸福論を語っている。
著者が盲ろう者となったばかりのある日、母親の機転で同教授は強力なコミュニケーション手段を獲得する。「指点字」だ。これは、盲ろう者の両手の甲を点字タイプライターに見立て、その上を指でタイプするように叩くというものだ。指点字は後に広まったが、公になったものとしてはそのときに世界で初めて使われた、と判明した。
当時の高校の仲間たちは皆、指点字を覚えてどんどん話しかけてくれるようになった。コミュニケーションが生まれたことで、暗い牢獄から解き放たれた気持ちになった。だがそれも束の間だった。 -
■「直接話法」の指点字で「開かれたコミュニケーション空間」を生み出す
著者は、すぐに再び孤独を味わうことになる。なぜなら、複数名がいる場合には周囲の状況がつかめなかったのだ。
そんな頃、クラスメートのI君と盲学校の先輩だったMさん(二人とも全盲)と3人で喫茶店にいたときのことだ。IさんとMさんが口頭で話している内容は、著者には分からない。そこでMさんが指点字で伝える。「M:I君はいつ帰省するの? I:うーんとね。22日に帰ろうと思うんだけどね」
このMさんの「直接話法」は画期的だった。この場合、たいていは「I君は22日に帰省するんだって」というように第三者的な情報として伝えるからだ。このMさんのやり方は、後に指点字通訳の原則として定着することになる。
著者はここで「開かれたコミュニケーション空間」を生み出すことに成功した。哲学者マルティン・ブーバーが著書『我と汝』で説いた「我-なんじ」の関係を築けるようになり、力強く生きていく力を身につけたのである。 -
◎著者プロフィール
東京大学教授。1962年兵庫県生まれ。3歳で右目を、9歳で左目を失明。18歳で失聴し全盲ろうとなる。1983年東京都立大学(現・首都大学東京)に合格し、盲ろう者として初の大学進学。金沢大学助教授などを経て、2008年より現職。盲ろう者として常勤の大学教員になったのは世界初。社会福祉法人全国盲ろう者協会理事、世界盲ろう者連盟アジア地域代表などを務める。著書に『盲ろう者として生きて』(明石書店)などがある。