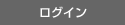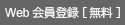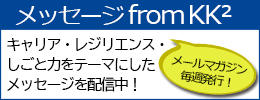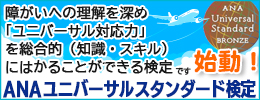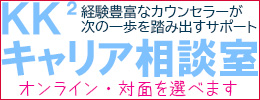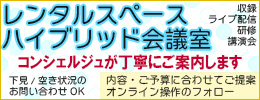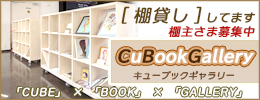『答えは必ずある』 ‐逆境をはね返したマツダの発想力(人見 光夫 著)
-
■業界の潮流に流されず、独自のエンジン開発で成功したマツダの戦略とは
ハイブリッド車や電気自動車に未来を託す日本の自動車業界にあって、マツダは内燃機関(エンジン)の性能を磨き上げる戦略を選んだ。その成果である、SKYACTIV(テクノロジー)とそれを搭載した新型デミオは大成功となった。本書では、その開発チームを率いた著者が、戦略と実行、成功の秘訣を語っている。
マツダは、モットーである「走る歓びと優れた環境安全性能をすべてのお客様に提供する」ことを、まだまだガソリン車で追求できると考えた。
2030年には自動車販売台数が今の2倍になると予測されている。その増加は主に開発途上国や新興国の経済成長によるものと考えられ、2倍になったとしても、内燃機関を搭載する自動車が90%を占めるというのが定説だ。また、ハイブリッド車の燃料はガソリンであり、その燃費はガソリンエンジンの性能に依存する。マツダの選んだ戦略には確たる根拠があったのである。 -
■ボウリングのピンにあたる「共通課題」を見つけ、集中して取り組む
マツダでは、経営危機への対処としてのフォードとの共同エンジン開発に人材をとられ、将来を見越した先行開発グループには30人ほどしか残らなかった。そこで著者は少ない人数で成果を上げるために「選択と集中」をすることにした。それは、たくさんの課題の中から主となる「共通課題」を見つけ出し、それに集中して取り組むというもの。それを解決すれば他の課題も連鎖的に解決に向かう、ボウリングでいえばヘッドピンにあたるのが、その「共通課題」である。
ヘッドピンを見つけるために、人見さんは、エンジンの効率改善の要素を整理することにした。エンジンにおける“損失”を四つに分類し、それを制御する七つの因子を特定。それらの因子を3段階で理想にもっていくことにして、ゴールまでのロードマップを描いた。最初のステップとして、七つの因子のうち三つの低減に取り組む。こうしてできあがったのがSKYACTIV-Gというエンジンだった。 -
◎著者プロフィール
マツダ株式会社常務執行役員、技術研究所・パワートレイン開発・電気駆動システム開発担当。1954年5月岡山県生まれ。東京大学工学部航空工学科卒。大学院修了後の79年、マツダに入社。一貫してガソリンエンジン関係の「先行開発」に従事する。94年まで技術研究所、その後パワートレイン開発本部へ。2000年パワートレイン先行開発部長、07年パワートレイン開発本部副本部長、10年パワートレイン開発本部長、11年執行役員、14年4月から現職。